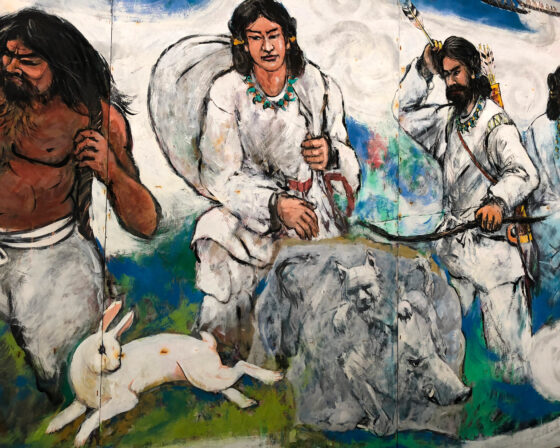ブログ

「商品はいいはずなのに、なぜか伝わらない」
そんな悩みを抱える経営者に向けて、神話と神社学の視点から、マーケティングの本質を読み解きます。
神話が数千年にわたり人を惹きつけ続けた秘密は、「正しさ」ではなく「共感でつながる物語」にありました。
神社という場の整え、心理学が示す感情の揺らぎ、風土に根差す一体感。
これらを重ねた神社学の知恵を、現代マーケティングにどう活かすか。
整え、問い、物語を紡ぐことが、結果として人を巻き込み、流れをつくり、未来を動かしていく。
本記事ではその具体的な道筋を、体験談とともに詳しくお届けします。
⸻
【目次】
1. マーケティングは「売り込む」ことではない
2. 神話は、最古のブランドストーリーだった
3. 【ストーリー】共感されなかったブランドが生まれ変わった日
4. 神話に学ぶ「誰に向けた物語か」の明確さ
5. 体験を共有する——神社に込められたマーケティング構造
6. 「自分ごと」として語られるとき、ブランドは生きる
7. 正しさより、物語の一貫性が人を動かす
8. 神話的マーケティングとは「場」と「流れ」をつくること
9. 運をひらくブランドに共通する整えとは
10. あなたの物語が、神話になるとき
⸻
【第1章】マーケティングは「売り込む」ことではない
マーケティングと聞くと、多くの人が「売るための仕組み」とイメージします。
けれど、本質的なマーケティングは違います。
「自然と共感され、受け取られる流れをつくること」
これこそが、真のマーケティングです。
無理に押し付けなくても、「この人の話をもっと聞きたい」「この世界に参加したい」——
そんな自然な動きが生まれる。
そこに、本当のブランド力が宿るのです。
そして、この「自然に巻き込む力」は、古代の神話と驚くほど似ています。
【第2章】神話は、最古のブランドストーリーだった
神話は、ただの伝説や昔話ではありません。
「この世界はなぜこうなっているのか」「なぜこの社会で生きるべきなのか」
という、人々を巻き込むための“物語装置”でした。
たとえば、日本神話において、天照大御神の系譜が天皇家につながる物語は、
単なる血統の話ではありません。
「私たちは、こんな壮大な流れの中にいる」という、人々のアイデンティティと誇りを生み出すための物語です。
つまり、神話とは「共感され、受け入れられ続けた最古のブランド」だったのです。
【第3章】【ストーリー】共感されなかったブランドが生まれ変わった日
ある若手経営者の事例をご紹介しましょう。
彼は、地元の特産品をブランド化しようと努力していました。
パンフレットもきれい。
味も折り紙つき。
にもかかわらず、なかなか売上が伸びない。
口コミも広がらない。
悩んだ末、彼が取り組んだのは「物語を語り直す」ことでした。
ただ「美味しい」「安全」という機能ではなく、なぜその土地でこの味が生まれたのか、
どんな想いで作っているのか、自分たちの歴史と願いを、一つのストーリーに編み直したのです。
すると、不思議なことが起きました。
試食した人たちが、
「これ、誰かに贈りたくなるね」
と言い始めたのです。
商品を“買う”のではなく、物語を“受け取り”、贈りたくなる。
そこから、ブランドは静かに、しかし確実に広がっていきました。
【第4章】神話に学ぶ「誰に向けた物語か」の明確さ
古事記も日本書紀も、およそ1300年前に編纂された書物です。
現存するのは後世の写本だけですが、その中には、日本神話として、
この世界の始まりから、神々の営み、そして天皇の系譜へと続く壮大な物語が記されています。
ここで注目したいのは、両者の「表現の違い」です。
古事記は、物語調で編まれています。
大和言葉——つまり、当時の日本語に、外来の漢字をあてて書かれていました。
一方、日本書紀は、簡潔な漢文体でまとめられ、天皇一代ごとに事績が整理されています。
なぜ、同じ神話を扱いながら、古事記は物語調で、日本書紀は漢文だったのでしょうか。
その理由は、「誰に向けて伝えるか」が違ったからです。
古事記は、日本国内に向けてまとめられました。
当時、まだ国家としての体制を整え始めたばかりだった大和朝廷は、人々に自分たちのルーツを「わかりやすく、親しみやすく」伝える必要があったのです。
だからこそ、古事記は、耳で聞いても伝わる物語調で、日本人に馴染みのある大和言葉で紡がれたのです。
一方、日本書紀は、諸外国に向けて編まれました。
当時、強大な影響力を持っていた中国や朝鮮半島諸国に対して、
日本が「一つの国家である」ことを明文化し、対外的な正統性を示す必要があった。
だからこそ、格式高い漢文で、天皇の歴史を整然と記録し、
他国に認めてもらうための“国の成り立ち”を示したのです。
この違いは、現代のマーケティングにも直結します。
誰に向けて届けるのか。
どんな言葉で、どんな形で伝えるのか。
対象が違えば、語り方も、伝え方も変わる。
そして、そこに一貫性があるからこそ、物語は力を持ち、共感を生むのです。
マーケティングにおいても、「すべての人に届けたい」と思った瞬間に、誰にも届かなくなることがよくあります。
神話の編纂にも見られるように、対象を明確にし、その対象に最も響く形で物語を紡ぐこと
これこそが、人を巻き込み、流れを生み出すための鍵なのです。
【第5章】体験を共有する——神社に込められたマーケティング構造
神社は、単なる宗教施設ではありません。
そこには、体験を通じて共感を育てる仕組みが込められています。
鳥居をくぐることで、日常と非日常の境界を超える。
参道を歩きながら、無意識に心が整う。
手水舎で身を清める所作によって、意識が内側に向かう。
そして拝殿で静かに祈ることで、個人の願いを超えた“場の一体感”を感じる。
この流れは、まさにマーケティングにおける「カスタマージャーニー(顧客体験の設計)」と同じ構造です。
商品やサービスにおいても、いきなり「買ってください」と押しつけるのではなく、
まず“場”を整え、共感を育み、自然な流れの中で「この世界に参加したい」と思わせることが大切です。
神社という場は、そうした体験の連鎖を、何百年、何千年と積み重ねながら、
「また訪れたい」という信頼と共感を育ててきたのです。
【第6章】「自分ごと」として語られるとき、ブランドは生きる
神話が長い年月を経ても人々の心に残り続けているのは、ただ語られたからではありません。
人々が、自分たちの生活や想いを重ね合わせ、「これは自分たちの物語だ」と感じたからです。
マーケティングも同じです。
一方的に情報を伝えるだけでは、人の心は動きません。
受け取った人が、「これは私の物語だ」と感じられたとき、はじめてブランドは“生きた存在”になります。
単なるスペックや優位性ではなく、「この世界観に共感したい」「この未来に関わりたい」という感情が、行動を生み出していくのです。
【第7章】正しさより、物語の一貫性が人を動かす
マーケティングにおいて、やってしまいがちなのは、
「いかに商品が優れているか」を正確に、理路整然とアピールしようとすることです。
しかし、人は正しさだけでは動きません。
このことを、科学的に裏付けたのが、行動経済学のダニエル・カーネマン博士です。
カーネマン氏は、2002年にノーベル経済学賞を受賞した研究の中で、こう示しました。
「人間は、合理的に行動しているように見えて、実際には感情や直感に強く左右されている。」
彼の理論では、人間の意思決定には「システム1(直感的・感情的思考)」と「システム2(論理的・意識的思考)」の二つがあり、多くの場合、人はシステム1=感情的な直感によって瞬間的に判断を下していると説明されます。
つまり、いくら理屈で完璧に説明しても、それだけでは人の行動を促すことはできないのです。
マーケティングにおいても同様です。
正しいスペック、優れた機能を訴えても、それだけでは人の心には響かない。
必要なのは、「この世界観に共感できる」という感情。
そして、それを支える一貫した物語です。
神話が何千年も人々に受け継がれてきたのも、理屈の正しさではなく、
「この世界に自分も属している」と感じられる物語の力によるものです。
現代のマーケティングも、まったく同じです。
完璧を目指すより、一貫したストーリーを磨くこと。
感情と直感に届く物語があれば、人は自然と行動を起こすのです。
【第8章】神話的マーケティングとは「場」と「流れ」をつくること
神話において、もっとも重要なのは「主人公」ではありません。
むしろ、“場”そのものが、物語を動かしていきます。
たとえば、アマテラスが天岩戸に隠れたとき。
世界は闇に包まれ、すべての流れが止まりました。
そして、八百万の神々が力を合わせ、舞を奉納し、笑い声を満ちさせることで、
ようやくアマテラスは岩戸を開き、光が戻ったのです。
この流れが示すのは、「個の力」ではなく、「場の力」こそが人と流れを動かすということ。
現代のマーケティングも、まったく同じです。
自社の実力や商品の優位性をどれだけ誇ったところで、
それが共感の空気を生まなければ、人は自然には集まりません。
整えられた“場”があり、そこに「一緒に歩みたい」と思える流れが育っていること。
これこそが、神話的なマーケティングなのです。
この「場と流れ」の力を、あるお客さまとのコンサルティングで目の当たりにしました。
その方は、2年前から「経営者としての想いを言葉にする」ことに取り組んでいました。
最初は、何度も「これかな」と思う言葉を試しましたが、しばらく経つとどこか違和感が生まれてしまう。
「しっくりくる」言葉は出てくるけれど、どれも少し、借りもののような感じがする——
そんな繰り返しでした。
それもそのはずです。
脳は「早く答えを出したい」と焦るもの。
だから、当てはまりそうな言葉に飛びつきたくなる。
でも、それでは本当に伝わる言葉にはならない。
それでは、場も、流れも生まれない。
焦らず、妥協せず、丁寧に自分の想いを整え続ける。
そんな時間を重ねた先に、ある日、静かにその瞬間は訪れました。
ふと、彼の口から出た言葉。
それは、“すとんと落ちた”のです。
「自分が大切にしてきたのは、◯◯(※具体的内容)だったんだ」
その瞬間、部屋の空気が変わりました。
言葉に力が宿り、未来像が静かに“にじむ”ように立ち上がった。
そこからは早かった。
これまで開ききらなかった販路への道が、自然とひらき、
応援したいという声が、静かに、でも確実に集まってきたのです。
この体験が教えてくれたのは、場を整え、言葉を整えたとき、自然と“流れ”が動き出すということ。
神話に描かれた、場を整え、舞を整え、光を取り戻す流れ。
それは決して、作為的に人を動かすものではありません。
整えた場が、整えた言葉が、自然と共鳴を呼び、流れを生み、人と運をつないでいく。
マーケティングにおいても、焦って売り込むよりも、整えた世界観を静かに灯し続けること
それが、真に人を巻き込み、持続するブランドをつくっていくのです。
【第9章】運をひらくブランドに共通する整えとは
一見、順調に拡大しているブランドでも、あるタイミングで失速してしまうことがあります。
逆に、静かに、着実に成長し続けるブランドもあります。
この違いは、どこにあるのでしょうか。
それは、「整え続けているかどうか」にあります。
整えを怠った結果、場が乱れ、本来持っていた流れすら失ってしまう
これは、神話にも象徴的に描かれています。
たとえば、スサノオのエピソード。
彼は海の神として大きな力を持ちながら、怒りと混乱のままに高天原で暴れ、
田畑を荒らし、機織り所を壊し、場を乱しました。
結果、天照大御神は天岩戸に隠れ、世界は闇に包まれます。
ここで重要なのは、スサノオ個人が悪かったのではなく、「場の整えを失った」ことが問題だったという点です。
どれほど力ある存在でも、場の整えを怠れば、流れを止め、周囲の秩序まで崩してしまう。
そして逆に、場を整え直した八百万の神々が舞い、笑い、空気を変えたときに、再び光が戻りました。
現代のブランドやマーケティングも、まったく同じです。
一時的な成功に浮かれ、整えを怠れば、いずれ場は濁り、人は離れ、流れは止まります。
逆に、たとえ地味でも、理念と言葉を磨き続け、場を整え、仲間と共に歩む努力を続けたブランドには、静かな強さが宿り、運がひらいていく。
マーケティングとは、単なる施策ではなく、整え続けることそのものなのです。
【第10章】あなたの物語が、神話になるとき
あなたがいま、心の奥で育てている想い。
まだ言葉にはならなくても、確かに存在しているその想いこそが、
これからの未来をひらく鍵になります。
商品やサービスを売ることは、ただの目的ではありません。
本当は、どんな物語を紡ぎ、誰と未来をつくっていきたいか
その問いと向き合うことが、経営であり、マーケティングなのです。
そして、あなたの整えた物語は、必ず誰かに届き、静かに流れを変えていきます。
焦らず、取り繕わず、静かに、自分自身の物語を磨き続けてください。
その積み重ねが、やがて人を巻き込み、未来をひらいていくのです。
神社学では、神社という場を通じて、自分のリズムを取り戻し、流れを整える知恵をお伝えしています。
そこには、神社そのものが持つ構造だけでなく、
心理学の視点——人が本来持つ心の揺らぎと整え、
そして、日本の風土に根ざした精神性が重なり合っています。
神話は、そのすべてを支える重要な知恵のひとつです。
神話とは、単なる過去の伝承ではありません。
先人たちが、整え、問い、流れを生み出し、未来を託してきた智慧なのです。
だからこそ、神社学では、神社・心理学・風土、そして神話を重ね合わせながら、
現代を生きる私たちが自分自身の物語を磨き、未来をつくることを大切にしています。
神社ゼミや神旅®では、この神社学の視点を体感し、
自分自身の整えと、物語の芽生えを丁寧に育てる場を用意しています。
あなた自身が整えた物語。
それは、間違いなく、あなたにしか紡げない神話となり、やがて誰かの希望となり、静かに世界を動かしていきます。
焦らず、妥協せず、整え続け、磨き続けましょう。
あなたの物語は、必ず未来をひらいていきます。
5日間無料メール講座
『運が動き出す!整える力を身につける神社活用法』
がんばっているのに、成果が安定しない。
努力しているのに、流れが続かない—— その原因は、行動ではなく“整えの土台”かもしれません。
神社は「お願いをする場所」ではなく、 本来は“自分と環境のリズムを調える場所”。
この講座では、全国延べ2万社を巡って体系化された神社学から、
運の流れと調和するための“整える力”を、心理学と風土の視点でお伝えします。
がんばる前に、整える。
そのひと工夫が、運と成果の差になります。
▶【日本古来の神道から学ぶ『整え方』の第一歩はこちら 】
あなたの運をひらき、人生の流れに乗る 古代神道の知恵を学ぶ『神社ゼミ』
変化のスピードが加速する今、何を選ぶか以上に、「どんな状態で選ぶか」が問われる時代。
だからこそ、焦って動く前に、自分の軸を整えることが、未来をひらく大きな差になります。
神社ゼミは、古代神道に基づく“日本古来のマインドフルネス”を軸に、
心・魂・体のバランスを整えるための学びと実践ワークを、毎月お届けする通信講座です。
自然の流れと調和しながら、自分の感覚を取り戻していく。
その積み重ねが、選択の質を変え、運をひらき、人生をしなやかに進めていく力となります。
▶︎【神社ゼミの詳細はこちら】
その他のブログ
【光輝ブログ】宇佐市平和資料館を訪れて、改めて感じた慰霊の気持ちと平和への想い
目次宇佐市平和資料館で特攻隊員の疑似体験をして想いを馳せる初めて訪れた宇佐市平和資料館実物大の零戦模型のコックピットの衝撃疑似体験し考え続けることで先人の行動や……
2025年08月01日
「ひかり塾」同窓会で再確認した人との関わりの大切さと気づきの連鎖
目次ひかり塾を経験した皆さまの集まりが新たな気づきを与えてくれる共通認識と心理的安全性の確保で内気な人も旧知の友のように他の人との関わりがあるからこそ可能なこと……
2025年08月01日
神社と漢方の意外な3つの共通点。より広い視野で包括的に学ぶ意味とは
目次大きく3つの共通点がある神社と漢方古来、根付いてきた神道の影響により日本になじんでいった漢方歴史的に見ても共通点の多い漢方と神社一部が全部、全部が一部。包括……
2025年07月03日
「劇場版『名探偵コナン』」と「神旅®」~忘れ去られた神様との繋がり感を取り戻す~
「目の前にいるわけではないのに、遠い昔ここにいた方々と出会い、通じ合えたような気がした」 先日、「神旅®アウェイク」を行った宇佐の地で、歴史上の人物に共感し、ご……
2025年06月13日
【光輝ブログ】アメリカの海軍史研究者にも「幸運艦」といわしめるほど名を馳せた駆逐艦「時雨」
旧日本海軍が所有していた艦はほとんどが悲劇的な結末を迎えています。ですが、そんな中でも不思議なほどに被害を受けることなく生き残った艦が何隻かあります。 「幸運艦……
2025年06月02日
日本古来のマインドフルネスで整える自分軸。経営者に伝えたい決断力の高め方
アテアでは先人の知恵を大切にし、それらを人生や仕事に生かしていただくための知識や具体的なワークをお伝えしています。ですが、先人の知恵とはどういったものか具体的に……
2025年05月30日
【見えない世界の基本①】人も土地も物も。誰もが持つ情報空間とは
アテアでは、「神旅®」を始めとするセミナーやビジネスコンサルティングなど各種サービスを通して、皆さまが望む未来へと向かうためのお手伝いをさせていただいています。……
2023年11月27日