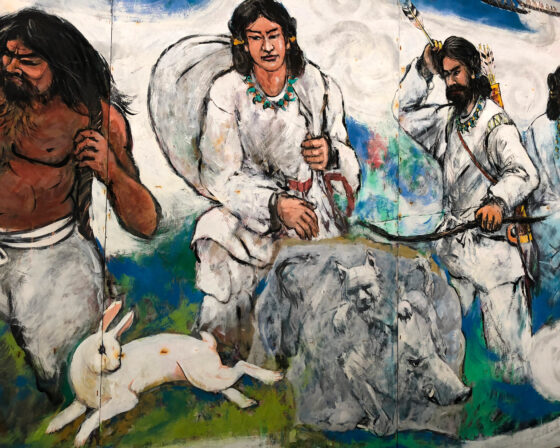ブログ

現代で注目されている「マインドフルネス」は、実は世界的に見ると仏教由来の思想にルーツを持ち、
スティーブ・ジョブズが「禅」から影響を受けたことをきっかけに、
Googleなどの世界的大企業が組織力向上のために取り入れたことで、広く知られるようになりました。
日本でもマインドフルネスは一時的なブームとなりましたが、
「なかなか習慣化できない」「瞑想に集中できない」という声を、私たちアテアでは数多く耳にしてきました。
その背景には、人間の思考や情緒は育った環境=風土によって深く影響を受けているという事実があります。
つまり、私たち日本人には、日本の風土に根ざしたマインドフルネスが自然に馴染む構造があるのです。
その代表が、神社なのです。
神社は、古来より「無になるための場」として機能し、
意識を「いまここ」に戻すための構造と所作が受け継がれてきました。
本記事では、アテアが体系化してきた神社学の視点から、
日本人の心と身体に自然にフィットする「整える力」とは何かを紐解き、
さらに実際のお客さまの体験談も交えながら、これからの時代に不可欠な“静かな再起動”としての神社的マインドフルネスをご紹介します。
今、忙しさに飲み込まれず、静かに流れを整え直す力こそ、未来を動かす基盤になります。
⸻
目次
1. マインドフルネスとは?——仏教由来と日本古来の違い
2. なぜスティーブ・ジョブズや世界的大企業はマインドフルネスを重視したのか
3. 神社は“今ここ”に戻すための設計だった——日本古来のマインドフルネスの構造
4. 所作そのものが意識を整える——祓いと拝礼に込められた意味
5. 何もしないことを受け止める空間としての神社——忙しい時代に求められる整え
6. 体験談:焦りと不安に押しつぶされかけた経営者が再起できた理由
7. 神社ゼミで学ぶ、日本古来のマインドフルネス——これからの時代を生き抜くために
⸻
【第1章】マインドフルネスとは?——仏教由来と日本古来の違い
近年、ビジネス界や医療、教育の分野でも広く取り入れられている「マインドフルネス」。
そのルーツは、仏教にあります。
「今この瞬間に注意を向け、評価を加えず、ただ気づいていること」
これがマインドフルネスの基本的な考え方であり、
本来は修行の一環として、心の自由を得るために行われてきたものでした。
マインドフルネスが現代に広く広がるきっかけを作ったのは、
スティーブ・ジョブズだと言われています。
ジョブズは、若い頃から日本の禅に深く傾倒していました。
余計なものをそぎ落とし、「本質だけを見極める」思考法を禅から学び、
それが後のAppleのプロダクトや哲学に大きな影響を与えたといいます。
彼の成功に注目が集まる中、
Googleをはじめとする世界的な企業もまた、
マインドフルネスを社員教育や組織開発に取り入れるようになりました。
彼らは気づいていたのです。
忙しさで心が散らばった状態では、静かな直感も、本当の創造力も生まれないことを。
こうしてマインドフルネスは、
「ストレス軽減」「集中力向上」「創造性開発」
といった現代人のニーズに応えるメソッドとして、世界中に広がっていきました。
そして、日本でも「マインドフルネス」が一大ブームとなりました。
しかし——
「なかなか習慣化できない」
「座っていると逆に不安になる」
「心を落ち着けようとするほど、焦りが増す」
そんな声を、私たちは多く聞いてきました。
アテアでは、全国2万社以上の神社を実際に歩き、
日本人が本来持っている心の整え方を探求してきました。
また、国内外で累計44万部以上の出版を重ね、
各地の神社や大手百貨店、行政機関とのコラボセミナーや講演を通じて、
さまざまな立場の方々に「整える力」の大切さを伝えてきました。
その中で確信したのは、
人は育った風土に合ったマインドフルネスを持っているということです。
日本人にとって無理なく心を整える場所は、
大陸の仏教的瞑想空間ではなく——
日常の延長にあった「神社」という場だったのです。
この違いを理解せずに、ただ海外からのマインドフルネスを真似しても、
どこかで無理が生じるのは当然なのかもしれません。
【第2章】神社の構造は“今ここ”に戻す設計だった
神社に足を踏み入れると、自然と心が落ち着く
そんな体験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は、これは単なる偶然ではありません。
神社は、意識を「いまここ」に戻すための設計が、
随所に緻密に組み込まれている空間なのです。
たとえば、鳥居。
鳥居をくぐる瞬間、私たちの無意識は「場が変わった」と認識します。
現代の心理学でも、空間的な境界を越えるとき、人は意識を切り替える傾向があることが知られています。
つまり鳥居は、「これまでの日常をいったん手放し、今この瞬間に戻るためのゲート」なのです。
続いて、参道。
神社の参道には、玉砂利が敷き詰められています。
ザクッザクッと足裏に伝わる感覚、耳に届くリズム。
その繰り返しによって、私たちの意識は自然に「今、ここを歩いている」という身体感覚に戻されます。
普段、忙しい思考で頭がいっぱいになっている現代人にとって、
これはとても強力な整えの仕掛けです。
さらに、手水舎。
ここで手を清め、口をすすぐという動作もまた、ただの作法ではありません。
• 一度立ち止まり、
• 流れる水に触れ、
• 身体を整える
このプロセスを経ることで、私たちは「今からここで特別な時間を過ごす」という意識の切り替えを自然に促されます。
このように、神社の空間設計には、
外から内へ、日常から非日常へ、 過去や未来から「いま」へ
意識を丁寧に整え直していく流れが、巧みに組み込まれているのです。
アテアでは、全国2万社以上の神社を巡る中で、
この空間設計が土地ごと、時代ごとに微細に異なりながらも、
一貫して「今ここに戻るため」という共通点を持っていることを確かめてきました。
日本人が自然と惹かれるこの構造こそ、私たちの身体感覚と風土が培ってきた、
無理なく心を整える知恵だったのです。
マインドフルネスは、単に座って呼吸を整えるだけではありません。
空間に身を委ね、無意識のうちに心をリセットしていく——
それもまた、日本古来のマインドフルネスの大切な在り方だったのです。
実は、ここでご紹介した鳥居や参道、手水舎だけでなく、
神社の中には、まだまだ細やかに「いまここに戻す」ための工夫が隠れています。
• 本殿の配置
• 灯籠の位置
• 狛犬や神使たちの存在
• 神楽殿や摂社・末社の配置 ……など
一見すると見過ごしてしまうようなものにも、
すべてに意味があり、私たちの意識を静かに整える役割を果たしているのです。
それらを意識的に感じ取れるようになると、神社で過ごす時間が、さらに深い整えと再起動の場へと変わっていきます。
【第3章】所作そのものが意識を整える——祓いと拝礼の意味
神社における整えは、
空間の設計だけにとどまりません。
身体の動き——所作そのものにも、
「いまここ」に戻すための深い意味が込められています。
たとえば、拝礼の基本作法である「二拝二拍手一拝」。
この流れを意識せず行っていた方も多いかもしれませんが、
それぞれの動きには、
心と身体を一体に整える知恵が隠されています。
まず、二拝(にれい)。
深く、静かに頭を下げる動作は、自然と呼吸を深くさせ、身体全体の緊張をほどきます。
この瞬間、心もまた、過去や未来の雑念から切り離され、
「いまここ」に意識が戻る準備が整えられていきます。
次に、二拍手(にはくしゅ)。
パン、パンと手を合わせ、響かせる音。
この音の振動は、空間と自分自身にリズムをもたらし、
意識を一点に集中させる役割を果たします。
まるで、心の中に散らばっていた感情や思考が、
音に合わせて整列していくかのようです。
そして最後に、一拝(いっぱく)。
深く静かに、もう一度礼をする。
ここで私たちは、集中した意識を、再び静かな受容の状態へと着地させます。
この一連の流れを通じて、
• 呼吸を整え
• 身体を整え
• 意識を整える
無理なく、自然な形で、「いまここ」に戻ることができるよう設計されているのです。
また、参拝の前に行う「祓い」も同様です。
祓いは、単なるお清めの儀式ではありません。
• 日常の埃のように積もった、
• 知らず知らずに心に引っかかっていた想念を、
• いったん外に払い流す
そのための心理的リセットでもあるのです。
私たちは、知らず知らずのうちに、外の情報や感情を背負い込んでいます。
それを手放し、空っぽの状態に戻るそれが祓いの本質なのです。
こうして、神社の空間を歩み、手を清め、所作を整え、静かに心を戻していく。
この一連の流れが、日本古来のマインドフルネスのかたちだったのです。
アテアでは、全国2万社以上の神社を巡る中で、この「整え直すための所作の知恵」が、
いかに日本人の身体感覚と自然に結びついているかを確信してきました。
無理やり心をコントロールしようとするのではなく、
動作を通じて心を「いま」に導く。
それが、日本古来の「ひもとく」べき整えの知恵だったのです。
【第4章】何もしないことを受け止める空間としての神社
現代社会は、「何かをし続けること」が当然のように求められる世界です。
スケジュールを埋める。
成果を出し続ける。
絶え間なく情報を取り込み、発信する。
私たちは、知らず知らずのうちに、
「動き続けなければいけない」という空気に飲み込まれています。
そんな中で、ふと立ち止まったときに襲ってくる、不安や焦燥感。
• 「何もしていない自分には価値がないのではないか」
• 「止まっている間に、誰かに追い越されてしまうのではないか」
この感覚は、多くの現代人にとって共通するものかもしれません。
神社は、そんな「何もしないこと」への罪悪感や焦りを、
静かに受け止めてくれる場所です。
鳥居をくぐり、参道を歩き、拝殿の前に立ったとき、
誰に何かを強制されることはありません。
• 願いごとをしなければならないわけでもない
• 必ず何かを考えなければならないわけでもない
ただ、そこに在る。
ただ、空気を感じ、立ち止まる。
それだけで十分だと、神社という場そのものが語りかけてきます。
現代では、「何もしない」という行為さえ、意図的に計画しなければ実現できないかもしれません。
しかし、神社は違います。
何かをするための場所ではなく、
「何もしない自分を、そのまま許す」場所なのです。
これは、単なる気休めではありません。
心理学の観点でも、
• 意識的に行動を止める
• 無為の時間を持つ
ことは、脳の疲労回復、思考の整理、創造性の回復にとって不可欠だとされています。
神社の静けさは、私たちの心と身体が自然にリセットされ、
再び流れを取り戻すための「間」を与えてくれるのです。
アテアでは、各地の神社でフィールドワークを重ねる中で、
この「何もしないことの力」を数多く体験してきました。
• 声を発しなくても
• 行動しなくても
• 結果を出さなくても
その存在自体が、整えられていく。
この感覚は、日本の土地と人が、何千年もかけて育んできた、
深い風土の知恵のひとつだと実感しています。
神社は、何かを頑張る場所ではない。
何かをしなければならない場所でもない。
むしろ、「何もしないこと」すらも整えの一部として受け止めてくれる、
数少ない場所なのです。
【第5章】忙しさの中で流れを取り戻す、静かな実践のすすめ
もし、あなたが今——
• 気持ちがずっと追い立てられている
• 頭ではわかっていても、心がついてこない
• 決断の質が落ちている気がする
そんな感覚に悩んでいるとしたら、
神社での整えを、ひとつのきっかけにしてみてください。
これは、ある経営者の方の体験です。
会社の業績が落ち込み、資金繰りや社員への責任に追われ、
毎日が「何かをしなければ」という焦りに支配されていたそうです。
「マインドフルネスがいいらしい」と聞き、
書籍を読み、瞑想にも取り組んだものの
座れば座るほど、不安感が押し寄せ、心を落ち着けようとすればするほど、
逆に焦りが増していったといいます。
そんなとき、アテアにご相談をいただきました。
私たちは、まず神社を活用した日本古来のマインドフルネスの考え方をお伝えしました。
そして、なぜ仏教由来の手法がすんなり馴染まないのか、
日本という風土に合った整え方が存在しているのか、
その歴史的背景も丁寧にひもときました。
「風土に合う」という意味と、「発生の歴史を知ること」の大切さ。
それが腑に落ちたとき、その方の表情は明らかに変わりました。
それからは、
• 神社の参道をただ歩き、
• 手水で静かに手を清め、
• 拝礼の所作に意識を重ねる
そんなシンプルな時間を、忙しい合間に取り入れることを続けられたのです。
結果として、不安を完全に消すことはできなくても、
不安を受け止めながら冷静に状況を見極める力が戻りました。
社員一人ひとりを信じ、共に再出発する勇気を持ち続けることができ、
やがて業績も回復していったのです。
「無理に心を静めようとしなくてもいい。
風土に合った整え方なら、自然に整っていくんだと身をもって実感しました。」
そう語ってくださったその方の言葉は、今も私たちの心に残っています。
日本古来のマインドフルネスは、決して特別な修行ではありません。
日常のすぐそばにある、静かな再起動のための方法なのです。
【第6章】神社ゼミで学ぶ、日本古来のマインドフルネス——これからの時代を生き抜くために
整える力。
それは、静かに未来を動かすための基盤です。
そしてこの力は、一時的な取り組みで終わらせるのではなく、
習慣として根づかせていくことが、何よりも大切です。
神社ゼミでは、日本古来のマインドフルネスを、現代の生活に無理なく取り入れられる形で学び、
実践していただけるようプログラムを組んでいます。
毎月、自宅にいながら——
• 神社という場の整えの構造
• 心理学的な視点からの整え方
• 日本の風土に根ざした中庸の在り方
• そして、その時々の運気に合わせた意識の整え方
これらを、動画やワークとして配信し、
日常の中で実際に体感していただけるようになっています。
特に今は、「風の時代」とも呼ばれる、
数百年に一度の大転換期にあたるといわれています。
社会の流れも、人の価値観も、
これまでとは大きく変わろうとしています。
こんな時代だからこそ——
外から与えられる情報や流れに振り回されるのではなく、
自分の内側に静かに戻り、整え続ける力が、これまで以上に求められるのです。
そしてそれは、一朝一夕に身につくものではありません。
• 土地の風土に馴染み
• 文化の中で育まれ
• 祖先たちの営みとともに受け継がれてきた
あなた自身のDNAレベルに響く整え方を体得すること。
これこそが、これからの人生や経営を静かに、でも確実に支えていく柱になります。
神社ゼミは、そのための静かな土台を、一緒に育てていくための場です。
焦らず、取り繕わず、自分自身を整え続ける力を育み、やがて、周囲と未来を変える流れを起こしていく。
そんな旅路を、共に歩んでいきましょう。
▶︎【神社ゼミの詳細はこちら】
5日間無料メール講座
『運が動き出す!整える力を身につける神社活用法』
がんばっているのに、成果が安定しない。
努力しているのに、流れが続かない—— その原因は、行動ではなく“整えの土台”かもしれません。
神社は「お願いをする場所」ではなく、 本来は“自分と環境のリズムを調える場所”。
この講座では、全国延べ2万社を巡って体系化された神社学から、
運の流れと調和するための“整える力”を、心理学と風土の視点でお伝えします。
がんばる前に、整える。
そのひと工夫が、運と成果の差になります。
▶【日本古来の神道から学ぶ『整え方』の第一歩はこちら 】
その他のブログ
【光輝ブログ】宇佐市平和資料館を訪れて、改めて感じた慰霊の気持ちと平和への想い
目次宇佐市平和資料館で特攻隊員の疑似体験をして想いを馳せる初めて訪れた宇佐市平和資料館実物大の零戦模型のコックピットの衝撃疑似体験し考え続けることで先人の行動や……
2025年08月01日
「ひかり塾」同窓会で再確認した人との関わりの大切さと気づきの連鎖
目次ひかり塾を経験した皆さまの集まりが新たな気づきを与えてくれる共通認識と心理的安全性の確保で内気な人も旧知の友のように他の人との関わりがあるからこそ可能なこと……
2025年08月01日
神社と漢方の意外な3つの共通点。より広い視野で包括的に学ぶ意味とは
目次大きく3つの共通点がある神社と漢方古来、根付いてきた神道の影響により日本になじんでいった漢方歴史的に見ても共通点の多い漢方と神社一部が全部、全部が一部。包括……
2025年07月03日
「劇場版『名探偵コナン』」と「神旅®」~忘れ去られた神様との繋がり感を取り戻す~
「目の前にいるわけではないのに、遠い昔ここにいた方々と出会い、通じ合えたような気がした」 先日、「神旅®アウェイク」を行った宇佐の地で、歴史上の人物に共感し、ご……
2025年06月13日
【光輝ブログ】アメリカの海軍史研究者にも「幸運艦」といわしめるほど名を馳せた駆逐艦「時雨」
旧日本海軍が所有していた艦はほとんどが悲劇的な結末を迎えています。ですが、そんな中でも不思議なほどに被害を受けることなく生き残った艦が何隻かあります。 「幸運艦……
2025年06月02日
日本古来のマインドフルネスで整える自分軸。経営者に伝えたい決断力の高め方
アテアでは先人の知恵を大切にし、それらを人生や仕事に生かしていただくための知識や具体的なワークをお伝えしています。ですが、先人の知恵とはどういったものか具体的に……
2025年05月30日
【見えない世界の基本①】人も土地も物も。誰もが持つ情報空間とは
アテアでは、「神旅®」を始めとするセミナーやビジネスコンサルティングなど各種サービスを通して、皆さまが望む未来へと向かうためのお手伝いをさせていただいています。……
2023年11月27日